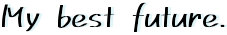高卒でも公務員になれる?
公務員試験の中には、高卒者を対象とした試験も存在します。
受験資格は基本的に学歴の制約はありませんが、試験内容や難易度は資格の種類によって異なります。
公務員試験は一般的に「高卒程度」「短大・専門卒程度」「大卒程度」といったカテゴリーに分かれており、高卒程度の試験は高校卒業程度の学力を求められます。
高卒者向けの公務員試験には、事務系や技術系、警察官・消防官など、さまざまな職種があります。
ただし、一部の職種や地域によっては学歴に関する制限や年齢制限がある場合がありますので、具体的な詳細を確認してから目指す職種を選定することが重要です。
公務員に興味がある場合は、各自治体や機関のホームページや担当窓口から詳細情報を入手し、最新の情報を確認することをお勧めします。
公務員に向いている人とは
公務員に向いているのはどんな人でしょうか?
公務員の仕事は、民間企業とは違う性質を持っています。そのため、向き不向きがあると言えます。
ここでは、公務員に向いている人の特徴を紹介します。
社会や国民のお役に立ちたいと思っている人
公務員の大きな特徴は、営利ではなく、全ての人や企業にサービスを提供するところにあります。
ですから、「お金を稼ぎたい」とか「社会に影響を与えたい」というよりも、「社会や国民のお役に立ちたい」と考える人に向いている仕事だと言えます。
さらに、各自治体では「県民目線で考える」などといった求められる人物像もよく見られます。自治体の問題や住民の悩みに基づいて行動できる力が必要です。
コミュニケーション能力がある人
公務員は同じ部署の仲間だけでなく、他の部署や民間企業のスタッフなどとも協力して仕事を進めます。そのため、どんな相手とも円滑にコミュニケーションをとれる能力が重要です。
実際、多くの自治体では、求められる人物像としてコミュニケーション能力を挙げています。
そして、全ての人や企業にサービスを提供する仕事なので、様々な価値観を持つ人と接することがよくあります。そのような相手の立場を理解し、適切な言動や対応ができる能力も必要です。
学び続ける意欲がある人
公務員になると、数年に一度の異動でさまざまな仕事を経験することになります。
もちろん、部署が変われば仕事の内容も変わります。また、法改正や社会情勢によっても業務内容が変わることがあります。そのため、日々学び続ける姿勢が大切です。
「公務員はいつも同じことを繰り返すだけ」と思っている人もいますが、実はそうではありません。学び続ける意欲がないと、公務員の仕事についていくのが難しいかもしれませんので、注意が必要です。
高卒で目指せる公務員の種類及び職種
高卒で目指せる公務員の種類は多岐にわたります。
以下に、高卒で応募可能な代表的な公務員の職種をいくつか挙げてみます。
具体的な職種や応募資格は地域や機関によって異なるため、希望する職種に合わせて詳細な情報を確認することが重要です。
地方公務員
市区町村や都道府県での職員。役所の職員、教員、消防士、警察官などがこれに該当します。
国家公務員
国全体の業務に従事する職員。一般職や特別職があり、行政官、税務職員、外交官などが含まれます。
警察官
国家の安全や秩序を維持するために働く職業。地方警察や国家機関で勤務することがあります。
消防官
災害や事故に対処し、市民の安全を守る職業。主に地方自治体の消防署に勤務します。
官庁職員
税務職員、皇宮護衛官、刑務官、入国警備官など、国家機関で働く職員。
これらは一例であり、他にも多くの職種が存在します。希望する分野や興味をもつ職種に向けて、公務員試験の募集情報や要件を確認し、適切な対策をとることが大切です。
高卒程度と大卒程度の違いについて
高卒程度と大卒程度の違いは、主に試験内容、難易度、給与などに関連しています。以下に、これらの違いをいくつか挙げてみましょう。
試験内容と難易度
高卒程度:通常、教養試験と作文で構成されます。一般的には、高卒者が受験できるレベルの内容ですが、それでも公務員職種に応じて必要な基礎的な知識が問われます。
大卒程度:教養試験に加え、専門試験があります。法律、経済、政治学など、専門的な知識が求められることがあり、難易度は高くなります。また、作文も論文形式となり、深い議論や論理的思考が求められます。
給与と昇進
大卒者の初任給が高卒者よりも高いことが一般的です。勤務年数が長くなるほど、大卒者の方が給与面で優遇されることがあります。
役職が上がるほど昇給するシステムであり、同じ年齢でも、高卒者と大卒者では昇進スピードに差が出ることがあります。
募集人数と競争率
大卒程度の方が受験資格を持つ人が多いため、公務員採用試験の募集人数も多いことがあります。
競争率は、高卒程度の方が一般的に低い傾向があります。一方で、大卒程度は多くの応募者が競争するため、合格率が低いことが予想されます。
これらの違いは、地域や職種によっても異なりますので、具体的な試験要項や給与体系を確認することが重要です。
公務員になるメリット
高卒で公務員になるメリットは、安定した収入や福利厚生、将来のキャリアパスなどが挙げられます。
公務員は、社会的な信頼や責任が高く、市民のために役立つ仕事をすることができます。
また、公務員は、給与やボーナスが安定しており、年功序列や終身雇用制度があるため、雇用の安定性が高いです。
さらに、公務員は、退職金や年金などの福利厚生も充実しており、老後の生活も安心です。
公務員には、さまざまな職種や分野がありますので、自分の興味や適性に合わせて選択することができます。
また、公務員は、研修や資格取得などの機会も多く、スキルアップやキャリアアップを目指すことができます。
高卒で公務員になるメリットは多くありますが、それだけに競争率も高くなります。
公務員になるデメリット
高卒で公務員になるデメリットは、仕事の負担やストレス、キャリアの限界などが挙げられます。
高卒で公務員になる場合は、大卒や院卒と比べて、試験の難易度や採用枠が限られていることが多いです。
そこから公務員になっても、高卒であることがハンデになることもあります。
公務員は、社会的な信頼や責任が高い分、仕事の負担やストレスも大きいといわれています。
市民からの苦情やクレームの対応や、緊急事態や災害に対応しなければなりません。
また、公務員は、組織や規則に縛られることが多く、自由度や創造性が低いと感じることもあるでしょう。
公務員には、さまざまな職種や分野がありますが、高卒であると、キャリアの選択肢や昇進の可能性が限られることもあります。
特に管理職や専門職になるためには、学歴や資格が必要な場面が多くなります。
高卒で公務員になるデメリットは少なくありませんが、それだけに自分の目標や能力を高めることが重要です。
公務員として働くためには、努力や継続が必要になります。高卒で公務員を目指す場合は、自分の強みや弱みを把握しておくことが大切です。
公務員になるには
公務員になりたいけれど、何から始めればいいのか分からない人もいますね。公務員になる方法と、公務員試験の対策についても紹介します。
まずは、各自治体のホームページで募集要項を確認しましょう。
自治体によって試験の名称が異なるため(高卒程度や初級職、高卒者など)詳細を確認することが大切です。
国家公務員を目指す場合は、人事院のホームページで高卒者試験の募集内容を確認します。
試験の申し込みはインターネットで行います。
どちらの試験も申込期間が限られているので、ホームページを定期的にチェックして見逃さないようにしましょう。
公務員の一次試験では、基本的に基礎学力や一般教養の筆記テストが行われます。
専門的な知識よりも、中学から高校までのいろいろな教科から出題されるので、広い範囲の知識が必要です。
そのため、試験の勉強をする際には、教科にとらわれず広い範囲の学習を心がけましょう。
また、一般教養の他にも、小論文・作文の試験もあるため、この対策も必要です。
テーマは試験の際に出題されるものですが、過去問を見れば、どのようなテーマが出題されるかが分かるので、それに合わせた対策ができます。
二次試験は面接です。
集団面接なのか、個人面接なのかは自治体によって異なるため、あらかじめ調べておきましょう。
面接では人間性や人柄が重視されます。そのため、自治体が求める人材像をしっかり押さえておくことが合格への近道になるでしょう。
公務員に関する質問
高卒で公務員になりたい人向けの質問に答えます。
高卒で公務員になった場合の初任給は?
高卒出身者が公務員になった場合の初任給は、おおよそ15万円前後です。大卒の場合と比べると、初任給には約3~5万円ほどの差があると言われています。
高卒公務員の倍率はどれくらい?
人事院が公表した「2021年度国家公務員採用試験実施状況」によれば、高卒程度の国家公務員試験の倍率は約4.8(申込者数38,939人/最終合格者8,165人)です。
前年度と比べてもわずかに低下しています。これは徐々に受験者数が減っている傾向にあることを示しています。
高卒で公務員になる前にやっておくことは?
公務員を目指す理由や動機をはっきりさせることが大切です。単に「安定しているから」といった理由ではなく、なぜ公務員になりたいのか、なぜその職種が適しているのかを具体的に考えましょう。これが1次試験や面接での良い回答につながります。
公務員試験に落ちてしまったらどうする?
公務員試験は合格者が限られているため、試験に落ちることもあるでしょう。しかし、「もしも試験に合格できなかったら」と心配する必要はありません。たとえ不合格でも、その後の選択肢はいくつかあります。公務員試験に合格できなかったとしても、他に進む道はたくさんあるのです。
公務員試験に合格できなかった場合の選択肢は主に、「公務員浪人」と「民間企業への就職」です。公務員試験の合格率を考えると、これらの選択をする方は多いです。
中には「民間企業に就職したら公務員になれなくなるのでは?」と心配する方もいますが、そんなことはありません。民間企業での経験があっても、受験資格を持っていれば公務員試験を受験することが可能です。さらに、社会人経験を活かした採用枠も存在するので、新たなチャンスがあるのです。
つまり、公務員試験に1度受からなかったからといってがっかりする必要はありません。その後も公務員試験に挑戦する機会がたくさんありますので、前向きに考えてみましょう。