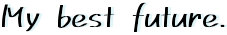大学全入学時代を迎えて
かつて大学進学といえば、高等学校に通う生徒の中でも特に成績のよい人やお金持ちの家庭の子供だけが進むことができることというふうなイメージもありました。
ですが、現在では「大学」という学校そのものに対しての敷居はかなり低くなっており、都心部などにおいては高校のあとには大学に進むことがほとんど当然の進路として勧められているところも多くなっています。
これは団塊世代の人たちが高校生の子供を持つくらいの時代である今から20年くらい前から見られてきた現象で、「自分が行きたくても行くことができなかった大学になんとか子供を入れたい」というような親側の希望が強く働いたために一気に大学への進学率は跳ね上がりました。
そうした大学進学を希望する生徒が増えたことにより、全国には新設大学が数多く登場してくることになったのですが、その数があまりにも増えすぎたことにより今度は現在深刻な社会問題となっている少子化に対応しきれなくなってきています。
実際、ここ20年以内にできた学校の中にはさっそく少子化による生徒数現象のために入学を打ち切ったり大学そのものを廃校にしてしまったりというところもいくつか見られるようになっています。
入学可能な人数よりも生徒数の方が圧倒的に少ない状況は「大学全入時代」とも言われており、金銭面や学力レベルで特に高望みをしなければ誰でもどこかの大学にはいれてしまうという状態が現在では出来上がっているのです。
大学進学率の推移と就職状況
詳しくみていくと、大学進学率は1955年の調査時にはわずかに7.9%でしたが、これが2009年には50.2%と半数以上の人が大学進学をするようになっています。
男女別に見たとき、男性の大学進学率が急上昇したのは1965~1975年の時期でしたが、女性の場合はやや遅れて急上昇を見せてきたのはだいたい1990年台に入ったあたりからです。
1955年時点では女性の大学進学率はわずか2.6%だったところ、1995年には22.9%、2009年には44.2%とまさに急上昇という感じで伸びているのが特徴的です。
これは女性は進学先として4年制大学よりも2年で修了する短期大学を好むという傾向があったためであり、実際1995年までは女性の進学先としては4年制大学よりも短大への進学率が高くなっていました。
これが1995年以降から逆転し、今では短大へ進学を希望する女性は急激に減少してきていることがわかっています。
しかしそれとは裏腹に1995年ころからは「就職氷河期」と言われる新卒での採用を極端に控える企業傾向が見られるようになっており、「大学には行ったけれど」という言葉が流行したほど学歴に見合う仕事を見つけることができない状態が続いています。
今見直される大学の価値
日本における大学はこれまで「入るのは難しいけど出るのは簡単」と揶揄されることがあるほど、入学試験の難しさに比べて内部での学習のゆるさが指摘されてきました。
一時期は「大学のレジャー化」と言われるほど、教育機関としての大学機能が大きく損なわれていることが問題視されたこともありました。
しかし大学卒業後の就職においてより優秀な人材となることは社会全体を支えることでもあるため、現在は国を挙げて大学という教育機関の見直しにかかっているところです。
今後はそんな大学改革に合わせ、進学を希望する学生もより進路に沿った大学選びが求められる時代になっていくことでしょう。